化学・物理分野の研究発表会で優秀賞を獲得。
興味を追求できる環境が大きな力に
~生徒対談~
2025/04/30 (WED)
BE A GLOBAL LEADER
OVERVIEW
立教新座中高では、自然観察園や理科実験教室といった施設・設備が充実しているのに加え、化学部や生物部、理科部などの部活動も活発です。今回は、高校1年次に「第75回埼玉県科学教育振興展覧会中央展/科学展(日本学生科学賞および全国高等学校総合文化祭埼玉県代表作品選考会)」で優秀賞を獲得した髙橋海さんと、中学3年生で「第75回埼玉県科学教育振興展覧会 中学校の部」優秀賞を獲得した廣瀬凛己さんに、それぞれの取り組み・研究について語っていただきました。
髙橋海さん(高校2年)× 廣瀬凛己さん(高校1年)
(2025年3月取材。学年は2025年度のものです。)
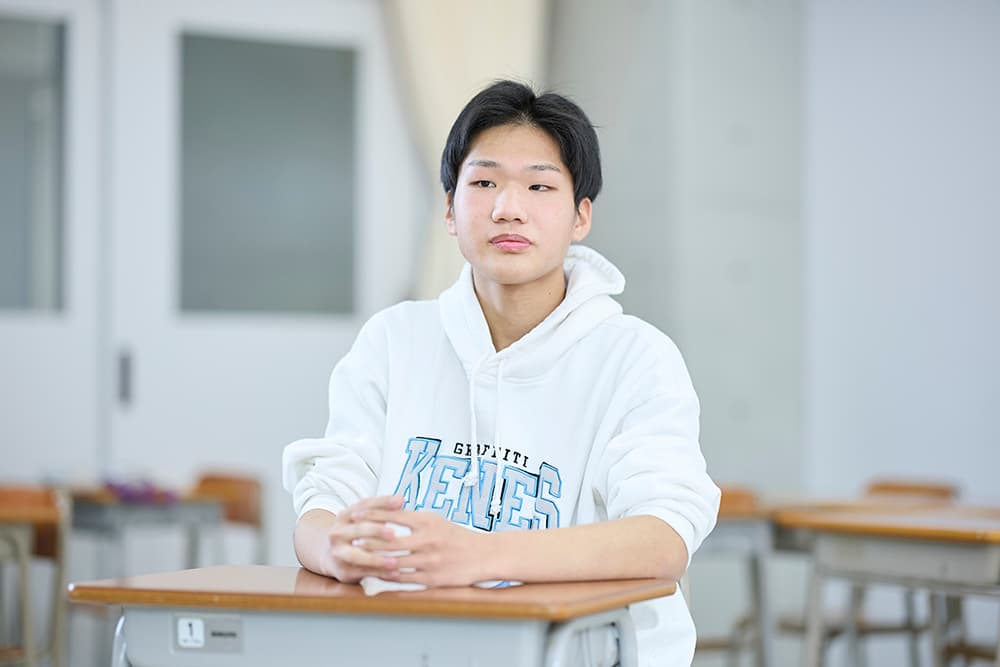
根気が求められる研究だからこそ、やりがいがある
髙橋:小学生の時から生き物が好きで、科学教育振興展覧会に出展したのも、「多摩川の微生物を利用した強力で持続可能な電池の開発」という内容の論文でした。多摩川は幼少期から友人と一緒に遊んでいた場所で、多摩川の微生物を取り上げた研究・論文で優秀賞をいただけたことは、本当にうれしかったです。廣瀬さんは中学校の部で優秀賞を受賞されましたが、どんな研究を行ったのですか?
廣瀬:私は「機体の形が変わると、空気の流れ方はどのように変化するのか」という物理分野の研究を行いました。中学2年の夏休みの自由研究で「機体の形が変わると、どう機体の動きが変化するのか」ということを研究していて、その発展として空気の流れに着目した研究を行った、という経緯です。昨年も出展したのですが県の展覧会までは届かなかったので、今回は県で優秀賞までいただき、とても光栄でした。最後まで妥協せずに根気強く研究を継続してきて良かったです。
髙橋:研究や実験には根気が求められますよね。私も微生物電池の試験体を作るのにとても苦労しましたし、毎日同じ時間に計測して記録する必要もあり、気を抜けない日々が続きました。また、プラスチックの容器に泥や水、極板などを入れて試験体を作るのですが、多摩川の泥を運ぶだけでも大変でしたし、思ったほどの電圧を得られず作り直すことも日常茶飯事です。
廣瀬:一つの試験体を作るのにどのくらい時間が掛かるのですか?
髙橋:泥を運んだり、泥の空気を抜いたりも含めると、ほぼ丸1日掛かってしまいます。それに実験は失敗することも多く、さまざまな条件を変えながら高い電圧を模索していく中で、最終的に50個くらいは試験体を作りました。根気のいる作業ではありましたが、失敗は新たな工夫にもつながり、そこにやりがいを感じられたことで最後まで続けられたのだと思います。
廣瀬:私は「機体の形が変わると、空気の流れ方はどのように変化するのか」という物理分野の研究を行いました。中学2年の夏休みの自由研究で「機体の形が変わると、どう機体の動きが変化するのか」ということを研究していて、その発展として空気の流れに着目した研究を行った、という経緯です。昨年も出展したのですが県の展覧会までは届かなかったので、今回は県で優秀賞までいただき、とても光栄でした。最後まで妥協せずに根気強く研究を継続してきて良かったです。
髙橋:研究や実験には根気が求められますよね。私も微生物電池の試験体を作るのにとても苦労しましたし、毎日同じ時間に計測して記録する必要もあり、気を抜けない日々が続きました。また、プラスチックの容器に泥や水、極板などを入れて試験体を作るのですが、多摩川の泥を運ぶだけでも大変でしたし、思ったほどの電圧を得られず作り直すことも日常茶飯事です。
廣瀬:一つの試験体を作るのにどのくらい時間が掛かるのですか?
髙橋:泥を運んだり、泥の空気を抜いたりも含めると、ほぼ丸1日掛かってしまいます。それに実験は失敗することも多く、さまざまな条件を変えながら高い電圧を模索していく中で、最終的に50個くらいは試験体を作りました。根気のいる作業ではありましたが、失敗は新たな工夫にもつながり、そこにやりがいを感じられたことで最後まで続けられたのだと思います。

先生方のサポートがあったから突き進めた
髙橋:廣瀬さんはどのように実験に取り組んでいましたか?
廣瀬:自作のペットボトルロケットを針金で固定し、そこにコールドスプレー(白色)を当てて空気の流れを可視化して、iPadでその様子を撮影・記録しました。ペットボトルロケットは大きく先端・胴体・スカートの3つの部位で構成されています。それぞれ何種類か作り、組み合わせを変えて計測したり、先端とスカートだけの構成で試したりと、何パターンも実験しました。組み合わせによって空気が乱れることもあればサッと流れることもあるなど、たくさんの発見がありました。
展覧会への出展にあたっては論文や発表資料を作る必要もあるので、実験以外にもいろんなことに試行錯誤しながら取り組みました。
髙橋:私も今回初めて論文を執筆しましたが、決められた枚数の中で最初はどう書いていいかもわからない状態でした。しかし、化学部顧問の加藤天先生(理科教諭)が基本的な論文の書き方や書く上でのコツを教えてくださったのに加え、最後まで何度も添削していただき本当にありがたかったです。また、化学部の先輩や友人が何度も発表練習に付き合ってくれ、アドバイスしてくれたことも大きく、とても感謝しています。
廣瀬:私は理科教諭の島野誠大先生にサポートしていただきました。島野先生との思い出で特に印象に残っているのが、中学2年で初めて科学教育振興展覧会に参加した時のこと。展覧会では発表をする場が設けられているのですが、初めてのことで発表の仕方が全くわからず、練習では原稿をただ読み上げるだけでした。それを聞いていた島野先生に「自分の実験内容はきっと頭に入っているはずだから、原稿なしで発表してみよう」と提案していただき、その後も何十回と練習に付き合っていただいたのです。その時のサポートや経験が、今回の展覧会でも生かされました。
廣瀬:自作のペットボトルロケットを針金で固定し、そこにコールドスプレー(白色)を当てて空気の流れを可視化して、iPadでその様子を撮影・記録しました。ペットボトルロケットは大きく先端・胴体・スカートの3つの部位で構成されています。それぞれ何種類か作り、組み合わせを変えて計測したり、先端とスカートだけの構成で試したりと、何パターンも実験しました。組み合わせによって空気が乱れることもあればサッと流れることもあるなど、たくさんの発見がありました。
展覧会への出展にあたっては論文や発表資料を作る必要もあるので、実験以外にもいろんなことに試行錯誤しながら取り組みました。
髙橋:私も今回初めて論文を執筆しましたが、決められた枚数の中で最初はどう書いていいかもわからない状態でした。しかし、化学部顧問の加藤天先生(理科教諭)が基本的な論文の書き方や書く上でのコツを教えてくださったのに加え、最後まで何度も添削していただき本当にありがたかったです。また、化学部の先輩や友人が何度も発表練習に付き合ってくれ、アドバイスしてくれたことも大きく、とても感謝しています。
廣瀬:私は理科教諭の島野誠大先生にサポートしていただきました。島野先生との思い出で特に印象に残っているのが、中学2年で初めて科学教育振興展覧会に参加した時のこと。展覧会では発表をする場が設けられているのですが、初めてのことで発表の仕方が全くわからず、練習では原稿をただ読み上げるだけでした。それを聞いていた島野先生に「自分の実験内容はきっと頭に入っているはずだから、原稿なしで発表してみよう」と提案していただき、その後も何十回と練習に付き合っていただいたのです。その時のサポートや経験が、今回の展覧会でも生かされました。
この充実した環境で、挑戦を続けていきたい
髙橋:専門分野に詳しい先生が在籍しているのはもちろん、理科系の施設・設備が充実している点も立教新座の魅力です。その影響からか、私は入学してからさらに理科系の分野に対する関心が高まり、今回の研究につながったと感じています。
廣瀬:3号館の3階1フロアはすべて理科関連の教室になっていて、実験室は化学、物理、生物、理科の4教室。そのほかに理科講義室と理科階段教室もあって、私は階段教室で発表練習をしていました。
髙橋:私もです。プロジェクターも設置されているので、本番さながらの環境で練習できるのは大きなメリットでした。ほかにも授業では一人一台顕微鏡を使えたり、化学部で使用できる薬品が豊富だったり、自分の興味次第であらゆることにチャレンジできる環境が整っています。理科系の部活動が盛んなのも、個人的にうれしいポイントでした。廣瀬さんは高校では何部に入るか決めていますか?
廣瀬:高校の部活動ガイダンスに参加してから決めようと考えています。大学受験も視野に入れているので、勉強との両立のしやすさを重視して選びたいですね。
髙橋:化学部は自由度が高いので両立しやすいと思いますし、自分の興味に合わせて実験ができるのでおすすめです(笑)。
廣瀬:ありがとうございます。自分のやりたいことを突き詰めるには高校1年の期間は最適だとも思うので、今回の研究の発展か、あるいは新しく興味をもったことにどんどんチャレンジしたいです。髙橋さんの今後の目標は何ですか?
髙橋:微生物電池の研究を進める中で、「ある植物の有無により電圧に差異が生じるのではないか」という仮説を立てました。しかし、実験を繰り返しても思うような結果が得られなかったため、今後はその原因や実用化に向けた可能性などを探っていきたいと考えています。さらに、高校2年の3学期から始まる卒業研究論文で、自分が納得いく研究内容にまとめることができたら嬉しいです。
廣瀬:3号館の3階1フロアはすべて理科関連の教室になっていて、実験室は化学、物理、生物、理科の4教室。そのほかに理科講義室と理科階段教室もあって、私は階段教室で発表練習をしていました。
髙橋:私もです。プロジェクターも設置されているので、本番さながらの環境で練習できるのは大きなメリットでした。ほかにも授業では一人一台顕微鏡を使えたり、化学部で使用できる薬品が豊富だったり、自分の興味次第であらゆることにチャレンジできる環境が整っています。理科系の部活動が盛んなのも、個人的にうれしいポイントでした。廣瀬さんは高校では何部に入るか決めていますか?
廣瀬:高校の部活動ガイダンスに参加してから決めようと考えています。大学受験も視野に入れているので、勉強との両立のしやすさを重視して選びたいですね。
髙橋:化学部は自由度が高いので両立しやすいと思いますし、自分の興味に合わせて実験ができるのでおすすめです(笑)。
廣瀬:ありがとうございます。自分のやりたいことを突き詰めるには高校1年の期間は最適だとも思うので、今回の研究の発展か、あるいは新しく興味をもったことにどんどんチャレンジしたいです。髙橋さんの今後の目標は何ですか?
髙橋:微生物電池の研究を進める中で、「ある植物の有無により電圧に差異が生じるのではないか」という仮説を立てました。しかし、実験を繰り返しても思うような結果が得られなかったため、今後はその原因や実用化に向けた可能性などを探っていきたいと考えています。さらに、高校2年の3学期から始まる卒業研究論文で、自分が納得いく研究内容にまとめることができたら嬉しいです。
関連記事
お使いのブラウザ「Internet Explorer」は閲覧推奨環境ではありません。
ウェブサイトが正しく表示されない、動作しない等の現象が起こる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ChromeまたはEdgeブラウザのご利用をおすすめいたします。